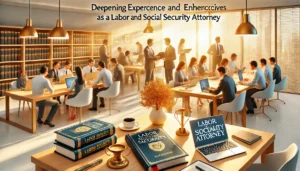開業時は「自宅開業」or「事務所を借りる」?

開業時の事務所はどうすれば良い?
開業に向けて準備をしていると「自宅開業するか、事務所を借りるか」という問題に必ず直面します。開業直後は売上が少なく、事務所を借りる負担は大きいのですが、自宅開業にもリスクはあります。どのような選択肢があり、それぞれのメリット・デメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
開業時の事務所さがしには「4つの選択肢」がある
開業時の事務所は、自宅兼事務所や、賃貸以外にも方法があります。
ここでは、以下の4つの選択肢を取り上げ、それぞれの特徴を見ていきます。
- 自宅兼事務所で開業する
- 賃貸で事務所を借りる
- シェアオフィスを利用する
- 合同事務所に入る
【1】自宅兼事務所で開業する
最もコストを抑えられる方法は、自宅を事務所にするパターンです。自宅に事務所を構えると大きな費用は発生しませんし、なによりも、通勤時間がゼロになるのも大きなメリットです。大都市に住んでおり、都心まで通勤していたサラリーマンからすると、独立開業の大きな魅力になります。
ただし、自宅兼事務所もデメリットがあります。
自宅の住所を公開するため、営業のDMが届き始める、来客対応がしにくい、表札を掲示する必要がある。家族が電話をしている途中に仕事の電話が掛かってくるなど、家庭と仕事の電話混在してしまうため電話回線を追加する。といったデメリットもあります。
また、自宅が賃貸物件の場合は物件の商用利用が禁止されているケースもあるため、賃貸借契約の内容確認が必要になります。
筆者の場合は、異性のスタッフや協力会社の方と一緒に仕事をすることになったときに、事務所とはいえ自宅に招き入れることができず、打ち合わせ場所に困ったという経験があります。
【2】賃貸で事務所を借りる
一般的な選択肢として、自宅とは別に事務所を借りる方法があります。敷金・礼金や什器の購入などの初期投資や毎月の賃料などの固定費はかかりますが、営業活動がしやすくなりますし、事務所や社労士会のホームページに住所を公開することにも抵抗がなくなります。
来客対応にも適しており、事務所を訪れるお客様や委託先を探しているお客様にも、「しっかりと経営している事務所である」と安心感を与える点は大きなメリットです。物件も事業用の事務所専用のビルもあれば、住宅利用と事務所利用の併用を認めるマンション型の物件もあります。
デメリットは、当然に賃料が発生しますので、小さくない固定費を負担することは、開業直後には大きなプレッシャーになります。また、登記ができない物件もあるため、法人を設立する場合は契約内容の確認が必要です。また、生活用の住宅とは異なり事務所利用になりますので、原状回復や解約手続きが早めに必要な場合もあります。
筆者はかつてワンルームマンションに事務所を構えており、ユニットバスのバスタブは物置として活用していました。また、1〜2人用の物件ではトイレが1つしかないことが多く、男女兼用になる点にも注意が必要です。
【3】シェアオフィスという選択肢
自宅開業や、事務所を借りる以外に、シェアオフィスを活用するという方法もあります。
シェアオフィスとは、月額の会員料金を支払うことで、フリーアドレス形式の机や、時間貸しの会議室などの「共用スペース」を利用できるサービスです。ロッカーやコピー機、郵便対応、電話代行なども付帯していることが多く、専用の小部屋を借りられるプランもあります。
ゼロから投資するよりコストパフォーマンスが良い
設備や什器が揃っていますし、会議室は必要な時に時間借りで対応できますので、同規模の事務所を自前で持つことを考えると、初期コストやランニングコストを抑えられます。また、創業直後は不在になりがちなので、電話応対サービス、来客対応サービス、郵便受付サービスは創業期には非常に便利なサービスです。
ビジネスチャンスも見つかりやすい
また、シェアオフィスは、他の小規模事業者と空間を共有するため、他の選択肢より交流が生まれやすく、ビジネスチャンスにつながる可能性が高いと言えます。施設によっては定期的に交流会や、入居者有志の自主的なイベントが開催されることもあり、新規開拓が至上命題の時期には魅力的な企画に接することもできます。ちなみに、全国展開しているシェアオフィスの企業によっては、各地の拠点を利用することも可能という場合もあります。出張の多い働き方になるなら、出張先で訪問地の拠点に立ち寄り、資料作成、資料の印刷をするといった使い方もできます。
シェアオフィスは、立地や施設の雰囲気により、入居している利用者層や業界の傾向も異なります。(例えば、渋谷ならIT企業を創業した若い方が多い。など)同じブランドでも場所によって空気感がまるで違うこともあります。
見学・内覧は比較的簡単に申し込めるため、気になるシェアオフィスがあれば一度訪れてみることをおすすめします。
もちろん、デメリットもある
もちろん、シェアオフィスにもデメリットがあります。シェアオフィスは設備や立地が良いため、賃料が床面積あたりで割高になる傾向があります。また、フリーアドレス形式のため、荷物を自由に置いておくことができず、書類の保管場所が限られてしまう点もデメリットです。
開業直後は小回りが利くかもしれませんが、取引先はもちろん、採用で求人を掛けたときも、シェアオフィスを敬遠する方は一定数いますので、シェアオフィスを長期に渡って、本社として利用することは難しいでしょう。
居心地の良さが足枷になるかも
「早々に売上をたてて、さっさと出ていけばいいじゃない。」と思うかもしれませんが、実は落とし穴があります。
シェアオフィスは設備が整って快適すぎるのです。そのため、自分で賃貸物件を契約し、自前の事務所に移転する際に、同レベルの物件を見つけるのが難しくなることはもちろん。居心地が良すぎて営業や外出が面倒に感じてしまうという“ぬるま湯”のような状態に陥る危険もあります。(誰しも、分かっていても生活レベルを下げることは難しいのです。)
もし「創業のハングリー精神を保ちたい」と感じる方は、最初は、あえて設備が最低限のアパートを借り、「2年後には隣のビルに移転するぞ!」といった目標を設定し、開拓活動の動機付けにするのも良いでしょう。
代表的なシェアオフィス
代表的なシェアオフィスには、以下のようなものがあります。
- リージャス
- WeWork
- サードコープ
- Business-Airport など
「開業したい場所+シェアオフィス」のキーワードで検索すると、いくつかのシェアオフィスが出てきますのでチェックしてみましょう。
また、地元密着のシェアオフィスや、地方自治体が廃小学校などを利用した創業拠点を提供していることもあります。
なお、「バーチャルオフィス」は住所だけを利用するサービスで、実際の机や設備は使用できません。机や会議室、什器といった設備を使用できるシェアオフィスとの大きな違いです。(シェアオフィスサービスの他に、住所利用だけのサービスに絞った「バーチャルオフィス」サービスを提供している、シェアオフィスもあります。)
【4】合同事務所に入居する
士業向けの選択肢として、合同事務所に入居するという方法もあります。
細かい点では違いがありますが、弁護士業界で“イソ弁”のようなものをイメージしてください。社労士事務所の一角を間借りして営業を行う形態です。
専門設備や備品が整っていることはシェアオフィスと似ていますが、わからないことがあればオーナーに質問できる環境にありますし、オーナー事務所の業務を下請けとして受けられるチャンスもあり、実務経験を積むチャンスにも恵まれているでしょう。
屋号の掲示や登記が可能かどうかは、オーナーの方針によりますので、事前に問い合わせが必要です。
独自のメリットはあるが、独自のデメリットもある
デメリットとしては、オーナーの事務所が主催するイベントの準備や、イベントの集客を求められることがあると言われます。居候をしている以上、断ることは容易ではないでしょう。また、他の開業社労士も入居しているため、同時期に入居した他の社労士と比較されることも自然な流れです。相互研鑽と言えば聞こえはいいですがプレッシャーを感じやすく、成果が出ていない、活躍できていない。となると、事務所に居づらくなることもあるようです。
また、シェアオフィスは事務所環境の提供が付加価値ですので、清掃業者が清掃をしてくれますが、合同事務所の場合は、社労士事務所の一角を間借りしている形になりますので、当然ながら賃料の支払いは発生しますし、共用スペースの清掃なども自ら対応する必要があります。
そして、オーナーとの間に雇用関係はないため、業務のやりとりはあくまで業務委託や下請けとしての関係になります。質問への回答も善意によるものだと理解しておく必要がありますし、オーナーとの折り合いが悪くなれば、「そこで仕事をすることは極めて難しくなる。」という力関係のリスクも把握しておきましょう。
各合同事務所は独自の方針で運営しているため、一律に善し悪しを論じることは難しく、リスクやオーナーとの相性をしっかり見極めて判断することが大切です。
まとめ
開業初期における事務所の選択は、将来の働き方や事業拡大に大きな影響を与えます。
目先のコストや利便性にとらわれすぎず、5年後・10年後のビジョンに基づいて選択することが大切です。そのため、先輩社労士の意見や経験を聞いてみることはもちろん、複数の選択肢を実際に見学してみることで、自分に合った事務所の形を見つけましょう。
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士法人アイプラス代表社員
- アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)、IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社等を経て、社会保険労務士法人アイプラスを創業。人事制度の構築から、労働問題の「具体的な対応策」を知りたい、経営者・人事担当者様向けの労働相談まで対応している。特定社会保険労務士
最新の投稿
 コラム2025年4月15日開業時は「自宅開業」or「事務所を借りる」?
コラム2025年4月15日開業時は「自宅開業」or「事務所を借りる」? コラム2025年4月4日研修で学べない専門家の必須スキルの獲得方法
コラム2025年4月4日研修で学べない専門家の必須スキルの獲得方法 コラム2024年5月9日開業当初は、どのように営業をすれば良いか?
コラム2024年5月9日開業当初は、どのように営業をすれば良いか? コラム2024年4月22日社労士の大学別のOB・OG会
コラム2024年4月22日社労士の大学別のOB・OG会