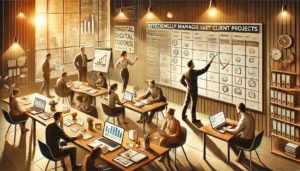社労士に必要な「ハイテク・ハイタッチ」とは?
以前の夜会で回答させていただいたことを記事にしたいと思います。
ご質問は「社労士業務はAIに代替されるか?」で、これに対する私の持論です。
社労士業務はAIに代替されるか?
社労士業務にAIに代替されるか?という問いに私はハッキリNO!と答えます。
なぜならテクノロジーが進むにつれ、ヒトは他人の温もりを求めるからです。
この「テクノロジーが進むにつれ、ヒトは他人の温もりを求める」という理論を「ハイテク・ハイタッチ」と言います。
ハイテク・ハイタッチは2000年代にサービス業で流行った言葉ですが、約20年経った今はほとんど聞かなくなりました。
しかし私は今になって余計に強く「この理論は正しい」と感じています。
以下、これからの時代の社労士にさらに必要になるであろう「ハイテク・ハイタッチ」について解説していきます。
社労士(サービス業)に必要なものは?
ハイテク・ハイタッチを解説する前に、経営や社労士を含むサービス業に必要なものをザッと整理します。
経営に必要な4つのもの
経営に必要な4つのものは①ヒト②モノ③カネ④情報でしょう。
経営に必要な4つのもの
- ①ヒト・・・人間。モノを作るにもカネを使うにも情報を得るにも必要。
- ②モノ・・・商品・建物などの有形物や知的財産などの無形物。モノを売ってカネに変えられる。
- ③カネ・・・お金。モノと交換できる。
- ④情報・・・データや事実など。ヒトが判断や行動するための指針。現代において情報がないと有利にモノを売ることができない。
飲食店に例えれば
- ①ヒトが④他人のレシピ(情報)を見て③カネを払って②食材(モノ)を買い、②知識と経験(モノ)で②オリジナリティを出した料理(モノ)を①お客さん(ヒト)に提供して③カネをもらう。
といったところです。
社労士に必要な5つのもの
経営に必要な4つのものに加えて、社労士に特に必要な5つのものは㋐人格㋑知識㋒スキル㋓経験㋔仲間でしょう。
社労士に必要な5つのもの
- ㋐人格・・・ヒトの能力。高い方が望ましいが、社労士に求められるのは挨拶や笑顔や約束を守るなど最低限の一般常識程度。
- ㋑知識・・・法律や労務に関する知識など。
- ㋒スキル・・・実務に関する技術など。
- ㋓経験・・・実務や人生経験。経験を積むことによって㋐㋑㋒㋔が増える。
- ㋔仲間・・・ライバルや同期やメンターなど。他士業やクライアントも仲間になりえる。
このうち㋐は経営に必要な①ヒト、㋑~㋓は経営に必要な②モノ、㋔は経営に必要な①ヒトもしくは④情報に含まれます。
ハイテク・ハイタッチ?初めて聞くんだけど?
さあ、経営に必要な4つのものと社労士に必要な5つのものを整理したところで本題のハイテク・ハイタッチの解説に入ります。
「ハイテク・ハイタッチなんて初めて聞く」という方が多いかと思いますが、ハイテク・ハイタッチとは
テクノロジーが進むほど、(意識的か無意識かに関わらず)ヒトは他人の温もりを求める
という理論です。
転じて今では
- テクノロジーを活用してヒトはヒトにしかできない仕事をやるとか、
- テクノロジーだけでなく人間的な部分との両立が大切
という考え方の礎になっています。
元ネタはアメリカの未来科学者ジョン・ネズビッツの著書『メガトレンド』(1982年出版)です。
ハイテク・ハイタッチって何?
「ハイテク・ハイタッチ」は2つの造語から成り立っています。
- ハイテク(High-Tech)とは、一般に言う先端技術ではなく、テクノロジー(Technology)が高まる(High)という意味です。
- ハイタッチ(High-Touch)とは、2人が腕を上げて手のひらを合わせる動作(この記事のアイキャッチ画像のような動作)ではなく、触れ合い(Touch)が高まる(High)という意味です。(ちなみに日本語で言うハイタッチは英語ではHIGH FIVEと言います)
これら2つの造語を合わせて
ハイテク・ハイタッチ=テクノロジーが進むほど(意識的か無意識かに関わらず)ヒトは温もりを求める
という意味になります。
ハイテク・ハイタッチとの出会い
私がハイテク・ハイタッチという言葉を知ったのは2009年頃です。飲食店の経営セミナーに行ったときに初めて聞きました。
初めてハイテク・ハイタッチという言葉を聞いた時は意味がよく解りませんでしたが、セミナーを受けているうちに意味が腹落ちしてきました。
2009年の当時から飲食業では調理ロボットや配膳ロボットの普及で「料理人や飲食店員の仕事は将来なくなる」と言われていました。
しかしこのセミナーでは全く違うことを言っていました。
そうです。
ハイテク・ハイタッチによって人間のやるべき仕事はさらに増え、重要になると言っていたのです!
それから15年以上たった今では調理器具が自動化しネコ型ロボットが配膳するようになりましたが、飲食店には従業員がいなくなるどころか人手不足の状況が続いています。
この状況に私はハイテク・ハイタッチは正しかったんだ!と強く思っています。
ハイテク・ハイタッチの意味の変遷
本来ハイテク・ハイタッチはテクノロジーが進むほど(意識的か無意識かに関わらず)人は温もりを求める、つまりハイテクによって更にハイタッチになるという意味でした。
しかし現在では機械に任せられることは機械に任せて、人にしかできない仕事は人がやるというように意味が変わっています。
さらには機械と人との両立が大切だという意味にも変わっています。
私が思う本来のハイテク・ハイタッチの意味
現在では機械に任せられることは機械に任せて人にしかできない仕事は人がやる、という意味に変わり言葉自体が廃れつつあるハイテク・ハイタッチですが、私はこの言葉の意味を本来のハイテクによって更にハイタッチになると捉えるとサービス業では上手くいくんではないかと考えます。
つまり、
確実に現代から更にハイテクになる将来は、更にハイタッチを求められる
ということです。
どういう事かというと、将来は
ハイタッチつまり信頼や感情や直接的な触れ合いやノンバーバルコミュニケーションなど人間臭さこそがサービス業のキモになると考えています。
飲食店でクレームが来るとき
では人間臭さはいつ出せば良いでしょうか?
突然ですがクイズです。
次の3つのうち飲食店でお客さんからクレームが来るのはどの順でしょう?
- ①味がまずかったとき
- ②店員の態度が悪かったとき
- ③盛り付けがグチャグチャなとき
その人やシチュエーションによって変わるかと思いますが、おそらく
②>③>①の順でクレームが多いでしょう。
まず②店員の態度が悪かったらそりゃぁお客さんは怒りますよね。「そんな店員を使ってるんじゃねー💢教育が悪い🤬」ってなります。
次に①か③が残るわけですが、実は①味がまずかったときはクレームがそれほど来ません。往々にして何も言わず帰ってリピートしないだけです。(むしろクレーム言ってくれるお客さんはメチャクチャありがたいです!適切な対応によってリピートしてくれます)
そして残った③盛り付けがグチャグチャなときはクレームが多いです。髪の毛や異物が入っているときなんかは②と同じくらい当然クレームが多いです。
最終的にはヒトがやらねばサービス業は繁盛しない
で、何が言いたいかというと、
お客さんは最後の結果しか見ない、というか、お客さんは最後に好ましい人間臭さを出されるほど良い評価をします。
クイズのようにヒトが関わる部分に対してお客さんは敏感です。
お客さんは意識的か無意識かに関わらずハイタッチを求めてるから人に対する評価を厳しくジャッジするのは当然とも言えます。
そして味よりも盛り付けに敏感なようにお客さんはより後に提供されたものを重視します。
お客さんにとって最後の結果こそがその店をジャッジするために重要な要素なのです。
ではお客さんに対して、あなたが最後にやるべきことは何でしょう?
あなたが最後にやるべきことは人間臭さを出しつつお客さんのハイタッチがしたい願望に応えることです。
はたしてお客さんに触れる最後にあなたが素晴らしいハイタッチを提供すれば、お客さんは高い評価を下してくれます。
あなたがお客さんで最後に素晴らしい接客をされたときの印象は強く残っているはずです。
お客さんに触れる最後のハイタッチをテクノロジーに任せてはいけません。ましてや最後のハイタッチをやらない選択をとってはなりません。
最終的にはヒトが人間臭さを出しつつお客さんの対応をしないとサービス業は繁盛しないのです。
社労士の顧客満足度を高める「ハイテク・ハイタッチ戦略」
社労士業界でもDX化や電子申請などテクノロジーが進んでいます。AIが手軽に使えるようになり様々なテクノロジーを使いこなすことが求められます。
しかし社労士もサービス業である限りテクノロジーよりも必要なのはハイタッチ=人間臭さです。
社労士業務は完全にはAIに代替されない
社労士業務はAIに代替されるでしょうか?
冒頭でも述べた通り答えはNO!です。
しかしある意味ではYESです。
社労士業務は完全にはAIに代替されませんがAIを代表とするテクノロジーによって1号・2号業務はいずれ代替されるでしょう。
いずれ1号・2号業務はAIに代替される
人間は少しでもラクをするためにテクノロジーを開発するわけですから、機械に任せられることは機械に任すのが当然です。
ナンボ車の運転が楽しくてもワイワイ酒盛りしながら目的地に行けるなら、あなたは自動運転に任せるでしょう。
同じように社労士業務もハイテク化され機械だけで業務が完結するようになるはずです。
実際にテクノロジーによって給与計算や就業規則の作成などはクラウド化し電子申請が主流になりつつあります。
いずれ1号・2号業務はAIに代替される日が来るでしょう。
社労士に必要なハイテクは平準化される
業務のハイテク化に伴い社労士はAIなどのテクノロジーを使いこなすことが求められています。
しかし社労士のなかにはテクノロジーの進化が早すぎてついていけない、テクノロジーを使いこなせない、といった意見を耳にすることがあります。
もちろん私も例外ではなく全てのテクノロジーを使いこなすことはできません。
では社労士はテクノロジーを使いこなす必要があるでしょうか?
私はある程度テクノロジーを使いこなすことは必要だけど重要ではないと考えています。
テクノロジーは誰でも簡単に使えることを目的としているからです。
固定電話から携帯電話そしてスマホへと移行したように、社労士が使うテクノロジーは誰でも簡単便利に操作できる時代が必ず来ます。
テクノロジーが誰でも簡単に使えることを目的としている限り、最終的にテクノロジーは平準化されるのです。
つまりハイテクが進む未来は誰でも同じような結果を得られるでしょう。
しかしハイタッチ=人間臭さは社労士ひとり1人個性があるし、誰にも(AIにも)教えてもらうことはできません。
テクノロジーは使いこなせる人に教えてもらえば済む話です。
ハイタッチこそ社労士に必要な差別化のキモ
サービス業にはハイテクもハイタッチも必要です。社労士業も同じです。
ハイテクが進むほどハイタッチを求められます。ハイテクは機械に任せて誰でも同じような結果が得られます。
ここまで解っていてあなたがやるべきことは何でしょう?
そうです。あなたがやるべきことは、
人間臭さ=温もり=信頼や感情や直接的な触れ合いなどハイタッチを前面に押し出すことです。
ハイタッチこそが社労士に必要な差別化のキモであり、ハイタッチを意識して最後に提供することでお客さんに選ばれる社労士となれるのです!
選ばれる社労士に必要な「ハイテク・ハイタッチ戦略」
では選ばれる社労士に必要なハイタッチとは具体的にどういうものでしょうか?
例えば
- 信用を得る
- フィードバックをもらいお礼を伝える
- 手書きの手紙を送る
などが考えられます。
しかしハイタッチの本質は、あなたの人格や情熱で決まると私は思います。
人格を磨き、お客さんに選ばれたい!お客さんのためになりたい!と強く願えばあなた独特の人間臭さが必ず現れるはずです。
選ばれる社労士に必要なハイテク・ハイタッチ戦略
- 社労士に必要な知識やスキルは徐々にハイテクに任せましょう。
- あなたが注力すべきは精一杯のハイタッチの提供です。
- そして人格を上げて、仲間を増やしながら、経験を積み、更により良いハイタッチを提供するのです!
これが選ばれる社労士になるためのハイテク・ハイタッチ戦略です。
サービス業における「ハイテク・ハイタッチ」の具体例
社労士業では徐々に進んでいるハイテク・ハイタッチ化ですが、他のサービス業ではかなり進んでいる種別があります。
ここでは飲食業・宿泊業・小笠原父島での例を挙げていきます。
飲食店でのハイテク・ハイタッチの例
飲食店は起業から10年後に生き残る店が1割とも言われています。
なので私はサービス業の最先端が飲食店だと思っています。繁盛している飲食店の店員の動きやオペレーション、料理の見せ方や接客などを観察すると楽しいですよ。
と、余談は置いといて、飲食店ではハイテク・ハイタッチ化がかなり進んでいます。
飲食店では数十年前から寿司がベルトコンベアで運ばれタッチパネルでの注文を導入したようにテクノロジーを積極的に取り入れています。
そして今や冷凍のままトレーに盛付けた料理を温めるだけだったり、必要な材料を入れるだけの全自動調理だったりが当たり前になるなどハイテク化が進んでいます。
(ただし飲食店では慢性的な人手不足のため、やむを得ずハイテク化が進んだという側面があります。)
繁盛している店では料理人がお客さんの名前や嫌いな食べ物を覚えていることがよくあります。
カウンターならタイミングよく話しかけたり、お客さんの表情や態度で体調が判ったりするもんです。
そしてレジでは積極的に感想を聞いたり、見えなくなるまでお見送りしたりするのがハイタッチの好例です。
宿泊業でのハイテク・ハイタッチの例
宿泊業もハイテク・ハイタッチが進んでいる業態です。
和倉温泉の加賀屋は1981年に配膳ロボットを導入しました。
他のホテルも今やフロントを無人化して1秒でチェックインできるようになりました。
バックグラウンドでは清掃や忘れ物をクラウドで管理するのが当たり前です。
しかしハイテクを導入している宿泊業のなかでも一流ホテルは未だにチェックイン後に人間のコンシェルジュが付きます。
そして予約時にお客さんが入力したものをデータベース化して、誕生日のサプライスをしたり、帰りにそっと車を回して驚かせたりのハイタッチを行っています。
このように宿泊業ではハイテクによって空いた人手によって更にきめ細かいハイタッチを実践することで顧客満足度を上げるよう目指しています。
小笠原父島におけるハイテク・ハイタッチ
私はちょうど1カ月前に初めて小笠原の父島に行きました。そこで帰りに遭遇したハイタッチが素晴らしかったのでご紹介します。
小笠原は東京都にありますが、船の定期便’おがさわら丸’で片道24時間かけて行き来するしか手段がありません。
小笠原から帰るときも当然おがさわら丸に乗り込みます。
そこで出会った光景がこちらです。(私には編集能力がないので、YouTube『時事通信トレンドニュース』より引用しています。)
はい。これ何回見ても感動します。
実際に甲板で見ていた私は年甲斐もなく泣いていました(笑)
これこそがハイタッチの極みだと思います。
別れ際+大声+感謝+いってらっしゃーい!+ザブーン!!って反則ですわ(笑)
もし機会があれば実際に体験してみてください。
また小笠原に行きたくなること請け合いです。
社労士に必要な「ハイテク・ハイタッチ」まとめ
まとめとして重要な点だけ箇条書きにします。
- ハイテク・ハイタッチとはテクノロジーが進むほどヒトは他人の温もりを求めるという理論
- ハイタッチとはヒトが他人の温もりを求めること
- 提供すべきハイタッチは人間臭さ
- 人間臭さとは信頼や感情や直接的間接的な触れ合いなど
- ハイタッチのベストタイミングは最後
- 最終的には人間がやらないと繁盛店にならない
- サービス業がハイテク後に目指すものはハイタッチ
- ハイタッチの本質は、あなたの人格や情熱で決まる
- ハイテクと素晴らしいハイタッチで選ばれる社労士になれる
- 小笠原のハイタッチは素晴らしい(言いたいだけ笑)
とオチが付いたところで今回は以上です。
ご拝読ありがとうございました!!
ようこそ!「社労士英知の夜会」へ!
社労士英知の夜会について
「社労士英知の夜会」は、山手統括支部が提供する2015年度から2022年度までの山手メンター塾を起源とした勉強会です。
近い立場の者同士が率直に話しあえる環境をつくるため「同期」という概念を取り入れています。また、専門家である以上、全員対等が原則と考えています。なので「先生禁止」も特徴です。
開業社労士・勤務社労士が集い『学びあい・実践しあえる仲間との出会いの場』です。社労士登録されている方であれば、登録区分、所属県会は問わず入会できます。
「社労士英知の夜会」は原則的に毎月第一金曜日の20時~22時までzoomにて開催しています。
当日に参加するかは強制ではありません。参加できる人が無理のない範囲で参加するスタイルです。よって毎月必ず参加する人もいれば、半年ぶりに参加する人もいます。
なお入会金も参加費も無料なのでヒヨコ狩りではありません(笑)
「社労士英知の夜会」当日の基本的な流れ
「社労士英知の夜会」当日の基本な流れは以下の通りです。
- 質問
- 参加者の誰かが不安なことや疑問に思ってることを質問する
- 回答者の指名
- 質問者が回答者を指名する
- 回答
- 指名された人は必ず回答する(正解・不正解はありません)
- 次の回答者を指名・回答
- 回答者が次の回答者を指名して回答する
- 2~3人回答する
- 回答→指名→回答…を2~3人繰り返す
- 質問者の感想
- みなさんの回答に対して質問者が感想を述べる
社労士英知の夜会に参加するメリット
開業して間もない人が「社労士英知の夜会」に参加するメリットは
- 不安なことや疑問点を気軽に聞ける
- 他の人の質問や回答で思いもよらなかったことなど、実務的な知識が増える
- 正解のない質問に答えることで、クライアントの咄嗟の質問に答える練習になる
- 同じような不安を抱えた人や経験豊富な人と仲間になれる
などです。
参加者の声
参加者からは
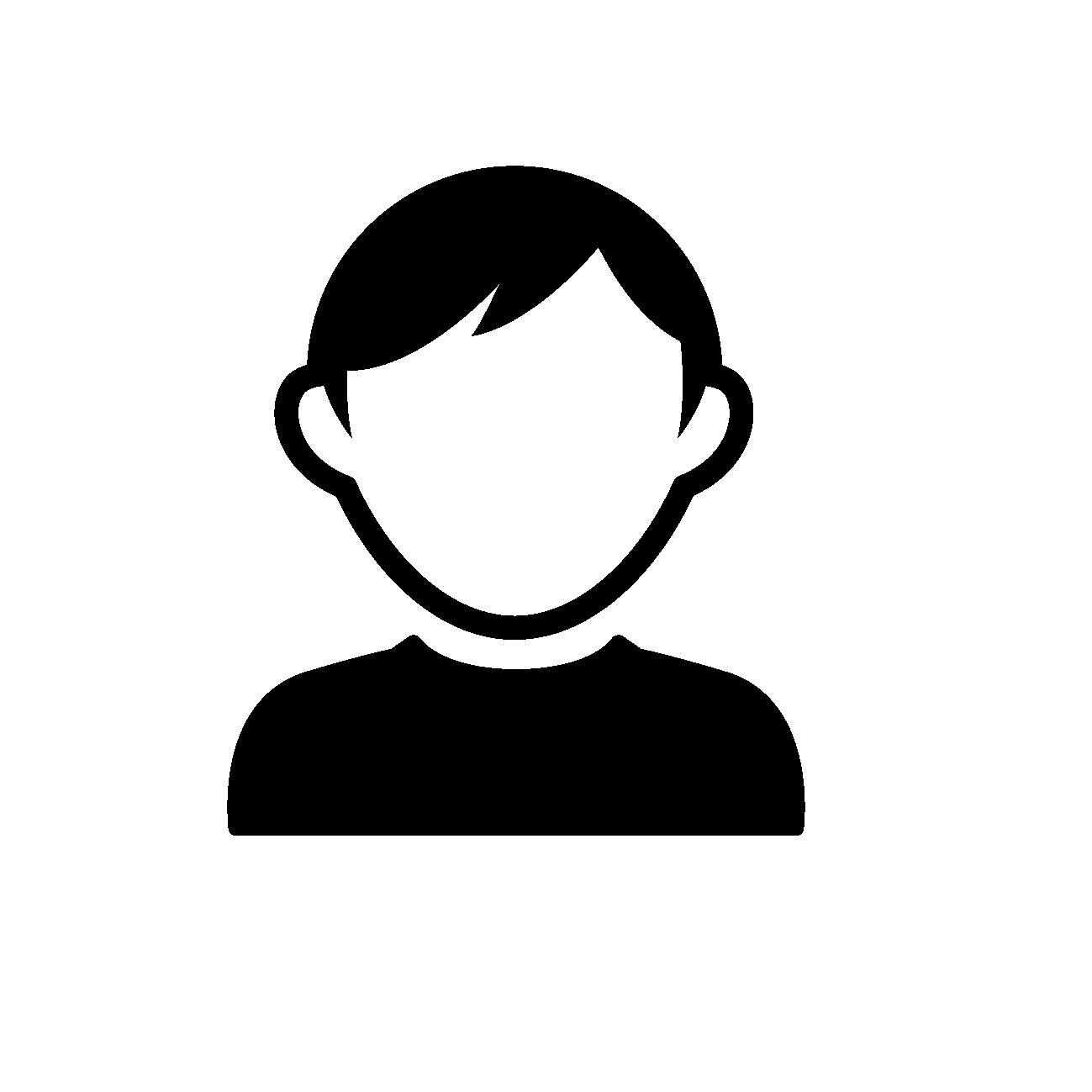
質問に答えてもらってスッキリした!

こんなやり方があったんだ!と目から鱗が落ちました!!

夜会でムチャぶりに答えるうちに相談業務に対する度胸がついた!
などの声が上がっています。
あなたも「社労士英知の夜会」ぜひ参加してみませんか?
社労士英知の夜会 が主催するオンライン勉強会では、全国各地の社労士が集まり経験や知識を共有し合うことができます。
この勉強会は一方向的に教えられる授業形式ではなく、参加者同士が意見を交換するグループワーク形式の共に学ぶ場です。
あなたもぜひ「社労士英知の夜会 」に参加してみませんか?
社労士に必要な知識と仲間が得られますよ!
投稿者プロフィール

- ちえぶくろFP社労士事務所 代表
- 埼玉県社会保険労務士会川口支部所属
料理人、魚屋勤務を経て「ちえぶくろFP社労士事務所」を開業
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社労士はR5合格 R6/8月登録
夜会にはR6/11月から参加しています。
最新の投稿
 コラム2025年3月14日社労士に必要な「ハイテク・ハイタッチ」とは?
コラム2025年3月14日社労士に必要な「ハイテク・ハイタッチ」とは?